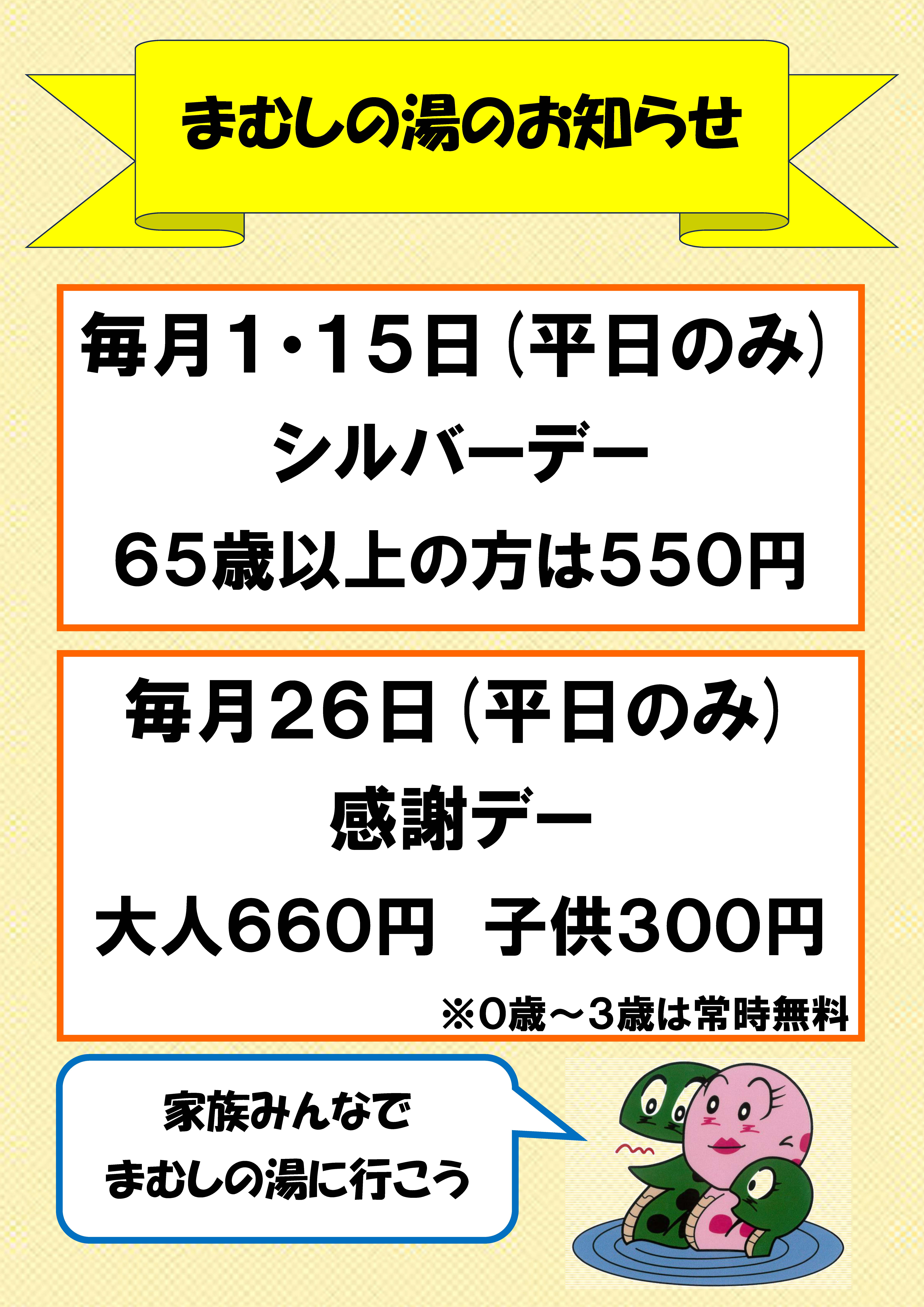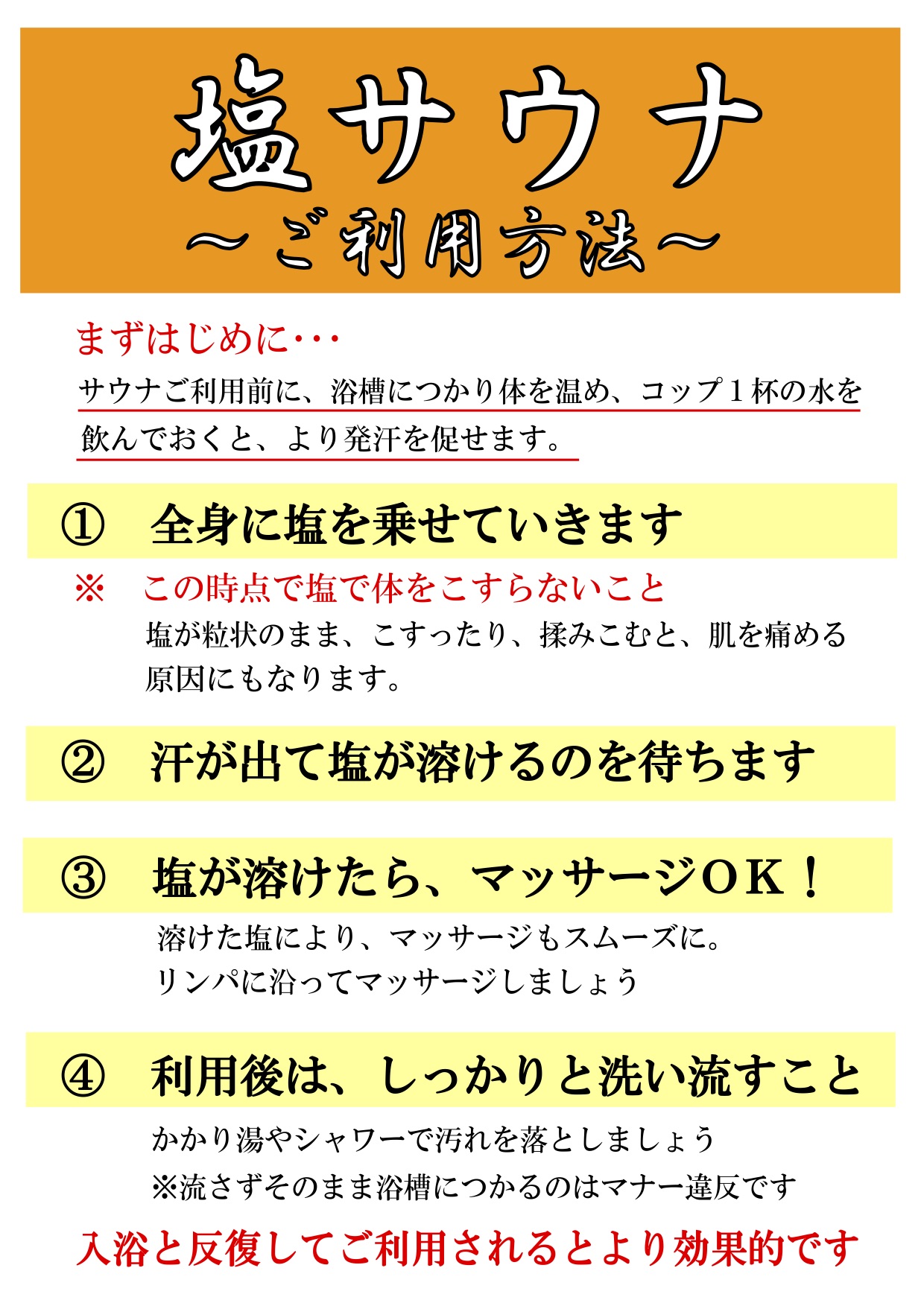郷土史より
貴船湯(まむし湯)は、僧空海(弘法大師)が、中国(唐)より遣唐使として帰国後、大宰府の観世音寺に二年七ヵ月滞在の折、当地で「まむし」に噛まれ苦しんでいるのを見て、孔雀明王教の法力を以て薬水を湧出させ、その水を使用させたところ痛みもとれて全快したという伝承がある。
以来、この水は、まむし、毒虫の害、「あせも」などに効果があり、広く民衆に活用されていった。其の後、江戸時代末期の安政二年(1855)五月に温泉発祥の記念碑がある。(温泉とあるも温度不詳)
古くより「まむし湯」としての名声は高く、近郷近在のみでなく、郡内外や県外からもまむしに咬まれ、戸板で運ばれてくる湯治者も多く、「まむし湯」は、名実ともに大いに繁盛する。
昭和59年9月6日糸島新聞より
糸島に冷泉(わかし湯)として古くから、その薬効を伝えられる浴場が二カ所。 (省略) も一つは二丈町福吉の中村地区にある吉井の湯として名を知られた「まむし湯」。夏から秋にかけての農業林業地区でマムシの被害は昔も今も変わらず糸島の話題。「ヒラクチ(マムシ)に噛まれたら吉井の湯へ行け」が大人の合い言葉であった。数日間この湯に浸かって冷泉を飲むと疼きと腫れが急速に減少し快癒するという。
糸島郡誌(昭和二年刊)にも吉井冷泉浴場として堂々とした家屋写真が出ていてマムシの害毒に特効ありと、珍しい外傷薬泉として、かなり古い歴史を持ち、人々に親しまれてきた湯である。 (省略) この湯を屋敷とする楢崎正策氏の夫人照代さんの話では、この冷泉近くの苗代では苗の伸びが他より異常に早いという。成分分析も正策氏がされて保管されてある。ムカデ、ハチなどの刺腫やオデキなどの外傷にもハッキリ薬効があるとの話。(以下省略)